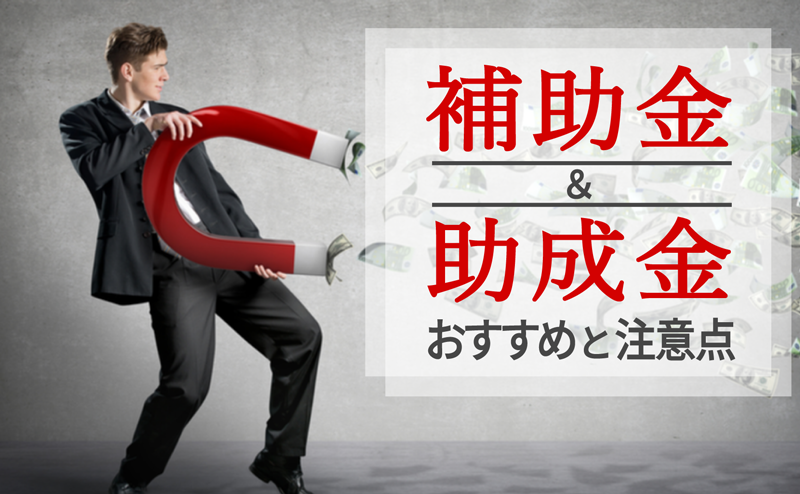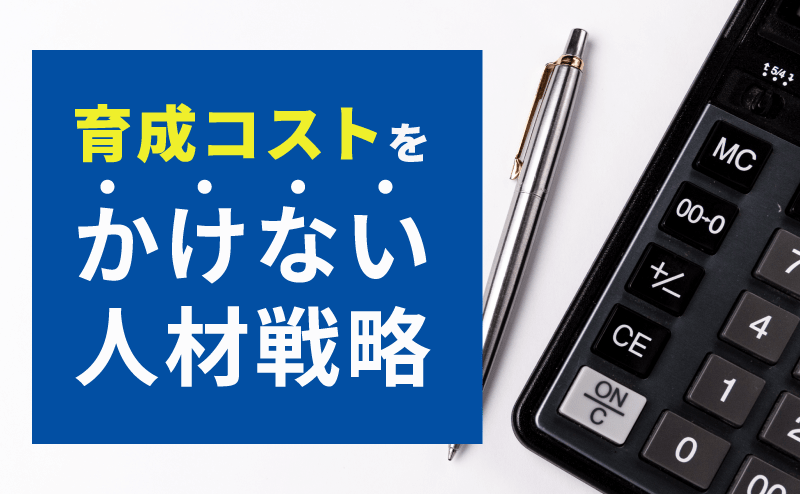どの組織においても、一般社員から管理職になった場合、部下の育成を任されることは多いでしょう。しかし、地位が上がったからと言って業務が簡単になるとは限りません。そして、管理職研修を受けた後でも、
- 具体的にどのように育成すればいいのか
- 管理職としてのフォローはどのようにするのか
- 管理職と部下の間に必要な関係性は何か(距離感がわからない)
など、悩みは尽きないでしょう。その一方で、人によっては「育成」を意識しなくても、単純なサポートやアドバイスだけで伸ばせることもあります。
このようなことを踏まえて、管理職がおこなう部下の育成方法や注意点などを解説していきます。

株式会社ホールハート代表取締役CEO 小野進一
人材紹介業歴18年の大ベテラン。広告業界に強力な人脈を持ち、1万人以上の求職者をサポートしてきた実績を誇る元宣伝会議取締役。2年連続(2014/2015)「ビズリーチ・ヘッドハンターサミット広告部門」のMVP受賞実績有り。これまでのキャリアを活かした他業界への転職/副業支援実績も豊富。
部下の育成方法の指針

人事が定めた育成方針をふまえて、管理職は以下のような目標を設定します。
- 実務に必要な知識やスキルの習得
- 自律的な思考を身につける
- 高い視点や考え方を持つ
など、スキルの向上や新しい考え方を獲得させるために教育をおこなう場合がほとんどです。しかし、部下の育成方法が明確に定まっていない企業もあります。
加えて、就任時に受けた管理職研修のみでは、部下のサポートやコミュニケーションまで十分におこなえるとは限りません。
また、ほとんどの企業ではOJT(On the Job Training:実際の業務を通した研修)を取り入れているものの、人材の育成に役立っているかまでは評価していない場合も多いです。
なかには企業として育成方針が統一されておらず、管理職の独断で休日に教育をおこなうといった良くないケースも。そのため、人事は育成方針を管理職と共有し、
- 実務にあわせた目標を決める
- 業務を任せた場合、どの程度までおこなえるのか
- 評価後に変化はあるのか
などを定期的に確認しながら、育成にあたることが重要です。また、コミュニケーションを通して信頼性を築くことも意識してもらいましょう。
部下の育成になぜ目標設定が必要なのか

目標に合わせて教育をおこなうことで、レベルの設定や成長度の把握などが可能になります。そのため、部下を育成する際には目標設定が必要です。
目標設定の際には、以下のポイントを管理職と共有しましょう。
- 部下の業務レベルを把握する
- どのレベルまで到達させるのかを想定する
- 定期的なコミュニケーションで現状を把握する
では、それぞれの項目について具体的にみていきます。ポイントは、部下と上司が一緒になって物事に取り組むということです。
部下の業務レベルを把握する
部下の育成をおこなう際には、計画に沿って進める必要があります。時期やタイミング、内容、獲得できるスキルのレベルなどを想定しながら、スムーズに実施できるように計画しましょう。
その際、管理職と部下で業務に必要な内容を共有しておきます。部下だけに業務内容を任せっぱなしにするのではなく共通の目標を認識することで、習得してほしい内容を部下に意識づけすることができます。たとえば、事務処理能力を伸ばす教育では、
- 知識・治験の有無や程度の確認
- タイピングの速さ
- 書類作成の経験
- ソフトやシステムの使用経験
などを加味して計画を立てていきます。
業務内容によって目標は異なるものの、部下の能力を把握しつつ、任せられる業務を増やしていくことが大切です。
そして部下が業務内容を引き継ぐとともに、ゆくゆくは組織の中核を担う立場になり、さらなる発展を目指していくことが人材育成の根幹となります。
どのレベルまで到達させるのかを想定する
部下の育成をおこなう場合、管理職は「どの程度までその業務を習得してもらうのか」を想定しておきましょう。そして人事は、その教育内容と結果をさらに精査します。
また、部下に意識や考え方を教えれば、それで育成が終了するわけではありません。
マネジメントをおこなう立場ならば、部下の動きに対して明確なフィードバックをおこない、さらなる成長を促していくことが必要です。
たとえば数字の改善をテーマとする場合、「どのように考えて、何を実行し、どのような結果をいつまでに達成したいのか」といった内容を、管理職と部下が共有しつつ目指していかなければなりません。
業務内容を教えれば全てが円滑に進むわけではなく、個々の特性を見極めたうえで、割り振る仕事内容やレベルを合わせていく必要があります。
加えて、業務を通して成長を促すため、管理職は「どのような思いで仕事に取り組んでほしいのか」まで共有しましょう。
このように人事は、「管理職と部下には共通意識を持ってもらい、意欲的に目標に取り組んでもらうこと」を目指します。
定期的なコミュニケーションで現状を把握する
部下がある程度の期間で業務に必要な能力を習得したとしても、管理職が定期的にチェックすることは非常に重要です。
たとえば、適性を見て人材を配置することができていたとします。しかし管理職によるチェックがなくなると、個人の適性が考慮されなくなり、社内で不満が出るケースは少なくありません。
この場合、管理職が部下の個性や考え方などを把握しきれていなかったことを意味します。人事はそういった問題を避けるために、「必ず定期的に確認をおこなう」などと決めておくとよいでしょう。
そして、管理職は定期的なコミュニケーションを重ねることによって、部下がどのように業務をおこなっているのか常に把握しておきましょう。
また、部下の立場からすると、管理職の方から相談に乗ってくれたり自分の課題を把握してくれたりすることは非常にモチベーションが上がります。部下と上司で良い関係が築けているだけで、部下は業務をやるための力が湧いてくるでしょう。人事のプロ人材のお問い合わせはこちら
部下の育成方法に必要な3つのポイント

次に、部下を育成する際の3つの重要なポイントについてみていきましょう。人事は、以下のような項目を管理職と共有し、育成をおこないます。
- コミュニケーションをとりながら目標を設定する
- 部下に合わせた課題を出し、フィードバックをおこなう
- 定期的な課題設定をおこなう
では、それぞれの項目を詳しく解説していきます。
コミュニケーションをとりながら目標を設定する
管理職が部下に目標を課すだけであれば、特別なコミュニケーションは必要ないように感じるかもしれません。しかし、コミュニケーションがなければ望むような育成はできないでしょう。
たとえば部下に対してコミュニケーションをとる場合は、
- 相手がどのように物事を考えているのか
- 自分のアドバイスを押し付けない
- 相手の意見を否定しない
が重要です。
考え方として間違っている場合は修正が必要ですが、コミュニケーションをとる第一の目的は相手を理解することです。
そのため、部下に対して無駄に時間を重ねるだけのコミュニケーションでは全く成長につながりません。場合によっては、部下が上司と話すのを避けることも考えられるでしょう。
また目標設定する際にも、管理職は部下とコミュニケーションをとり、実態を把握したうえで課題を設定していきましょう。
そうすることで部下の意欲を維持しつつ、業務に向き合ってもらうことができます。
そのため、人事は「管理職と部下はコミュニケーションをとりながら目標を設定する」ことを方針として定めておきましょう。
部下に合わせた課題を出し、フィードバックをおこなう
個々の能力や知識をふまえて、部下のスキルをレベル分けすることも可能です。しっかりと部下ができていること、できていないことを把握しておくことが肝心になります。そして、管理職はそのレベルによって部下に与える課題の内容を調整しましょう。この際に重要なのは、
- 課題をクリアすることで部下の能力が伸びる
- 今後業務上で必要となるスキルの下地をつくる
- 課題を出すことで新しい考え方や視点を持ってもらう
です。そして人事は、そういった取り組みができるようなサポートをおこないましょう。部下が何人もいる場合はサポートが大変になってしまいますが、少しでも面倒を見ると部下の成長を後押しできるようになります。管理職が与えた課題をクリアすることによって、部下のスキルアップや意識の変化が期待できるでしょう。
また、課題をクリアした場合でも、結果だけを評価することが全てではありません。業務の過程なども加味して、フィードバックをもとにさらに改善していく体制をつくりましょう。
定期的な課題設定をおこなう
部下の育成には定期的に課題を出すことが必要です。部下のスキルや考え方は変化していくものですし、常にチャレンジする環境を与えることで、自発的に動ける人材を育成するためです。
設定する課題は、新しいスキルの習得や、業務やマネジメントに必要な知識を得ることを目的としましょう。そして、その課題を通じて成長できることが大切です。
管理職が部下を評価する場合、褒めることも、あるいは注意することも必要です。もちろん課題設定の時だけではなく、通常の業務においてもそういった場面は発生します。
部下がどのような考えでその行動をとったのか、管理職は冷静に判断しなければなりません。
たとえば、必要な書類を期日までに作成する課題を出したとしましょう。そして部下は、期日までにすべて作成しました。この場合、管理職は、
- 書類の内容を確認したうえで、期日までに完了したことを褒める
- 仮に書類にミスがあった場合、改善のためのアドバイスをおこなう
- 事実確認が必要なら、その指示を出すか自分が確認をおこなう
といった対応が考えられます。管理職は次につなげるために、結果だけでなく、その過程なども把握しなければなりません。また、人事はその評価に基づいて次の育成計画を決めていきます。
部下の育成方法の事例

ここでは、部下の育成事例についてみていきましょう。
グリー株式会社
グリー株式会社は、目標管理制度を用いて部下の目標管理をおこなっているだけでなく、部下と管理職は1対1で定期的な振り返りを実施しています。
管理職と部下の信頼関係がなければ、1対1の振り返りは非常に難しいものです。そのため、人材育成においても的確な課題出しができているからこそ、実践できる育成方法だといえるでしょう。
また、目標設定・評価・振り返りなど、課題に対するあらゆる場面で管理職と部下が定期的に話し合う機会が多々あります。
そうした定期的なコミュニケーションが部下育成における信頼関係を築くきっかけとなり、好循環につながっています。
大日本印刷株式会社
大日本印刷株式会社で実施している中堅社員への育成は、管理職としての意識やサポートをテーマとしたものです。1泊2日の日程で、研修を受けた社員が部門に関係なくチームをつくります。
そして、決めたテーマに関して経営陣に提言する機会を設けており、社員の自主性を尊重した育成方法だといえるでしょう。
実際に、チームによって考えられた提言は経営陣が拾い上げ、社内の制度が実際に変更されたこともあります。
大日本印刷株式会社では、人材が持つ意志や考え方を反映した教育方法を重視し、うまく企業の成長につなげているといえるでしょう。
楽天株式会社
楽天株式会社は人材に対する綿密な研修制度を整えており、業務上の成果とそれに行き着くまでの過程をすべて管理職が評価します。
また、その評価によって月給や賞与の額に直接的な影響があることも特徴的です。
社員の勤続年数ではなく、その社員が持つ能力や成果が正当に評価され、昇格や適切なアドバイスにつながっています。
2018年からは、1対1のミーティングやフィードバックも制度として導入しています。そのため、人材の持つ可能性や現状のスキル評価に至るまで、細かく把握することができているといえます。
そして、企業として学び前進する組織であることを意識し、日々の業務に取り組んでいる状況です。
まとめ

部下の育成は、人事の制度や方針に基づいて管理職が実施するものです。育成方法をきちんと定めることで、組織として成長するだけでなく、企業の抱えている課題を改善していくことも可能です。
そして会社としての目標を掲げるだけでは、部下の成長を促すことができません。
管理職が課題の設定やアドバイスを一方的におこなっても、部下が期待通りに成長するわけではないことに注意しましょう。そのため部下の育成においては、
- 個人に合わせて明確な目標を設定する
- 期限を設定し、結果をフィードバックする
- 課題出しとフィードバックを繰り返しながら、成長を促す
といったことが大切です。そして、こういった育成制度や考え方が社内にない場合は、どうすれば実践できるのかを具体的に検討してみましょう。
制度の設計や育成方法を見直しながら実践・改善していくことで、企業としての意識や社内の雰囲気なども改善することが可能となります。
こちらもあわせて読まれています
<こんな方におすすめです>
- 経営課題にマッチしたプロ人材が見つからず、課題が前に進まない
- ようやく見つけても、高額な年収がネックとなってしまう
- いざ採用して、もしも期待値以下だったらどうしよう、と不安になる
- ピンポイントな専門家を常時活用できるポジションの用意は難しい
- そもそもどんな人材が必要なのかわからない
ハイスキルシェアリング「プロの助っ人」では、年収800万円を超える通常は雇用が難しいハイクラス人材を、必要な時、必要な分だけ20万円~業務委託で活用できる新しい人材活用の形をご提案しています。
人件費はできるだけコストカットしたい。
しかし現状の社内の戦力だけでは経営課題の解決は難しい。
そんなときに「ピンポイントで助っ人に力を借りる」活用が、成長企業を中心に始まっています。
このような経営課題でお悩みの企業様は、是非ハイスキルシェアリング「プロの助っ人」にご相談ください。
 7種類の通販サイト集客方法と予算を解説!有料施策と無料施策の組み合わせが重要
NEXT POST
7種類の通販サイト集客方法と予算を解説!有料施策と無料施策の組み合わせが重要
NEXT POST
 これから副業で稼ぎたい人へのバイブル!おすすめの副業や注目の新ビジネス、注意点まで全てが分かる!
これから副業で稼ぎたい人へのバイブル!おすすめの副業や注目の新ビジネス、注意点まで全てが分かる!