現代において、感染症などの災害や事業環境の激変に対して、企業はより対応力を高める必要があります。
そうした中で、副業制度を導入し、従業員の自立性や柔軟性を向上させることは戦略としてとても有効であると考えられます。
現在や今後の社会の激動と、その中で企業としてより力強くあるための副業制度について社会保険労務士の松井勇策が解説します。

【プロフィール】
松井勇策(社会保険労務士・公認心理師・Webアーキテクト) フォレストコンサルティング労務法務デザイン事務所代表。副業/複業・リモートワーク・上場対応・AI化支援・社内社外ブランディング・国際労務対応など「新しい生き方・働き方の確立の支援」を中心に、社労士や心理師として活動している。著作等も多数。
名古屋大学法学部卒業後、株式会社リクルートにて広告企画・人事コンサルティングに従事、のち経営管理部門で法務・上場監査・ITマネジメント等に関わる。その後独立。東京都社会保険労務士会役員(支部広報委員長・研修/広報委員・労務監査責任者等)
感染症の流行や事業環境の激変時に求められること
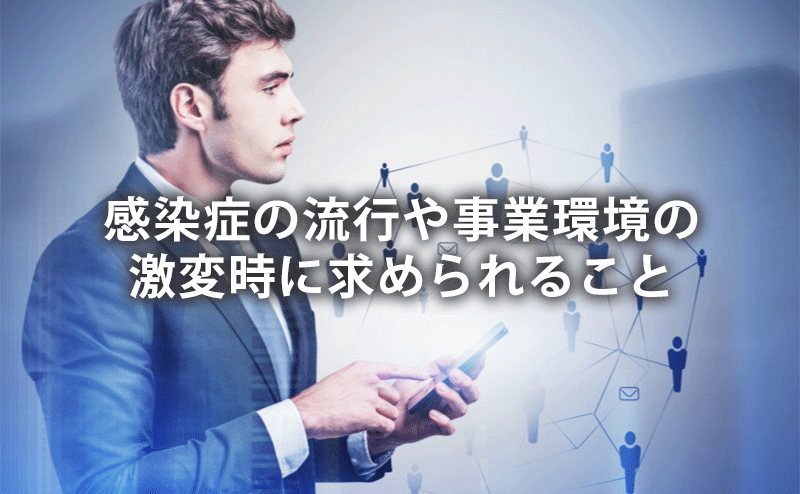
2020年5月現在、世界中でコロナウィルス感染症が流行し、政府や民間のさまざまなレベルでの対策が取られています。そうした中で、事業環境が激変しています。
通勤や営業の自粛措置によって業務を一定期間行うことが難しくなったり、社員の方々の不安が大きく、一次的に休業にせざるを得なくなったりといった企業が多くあることでしょう。
こうした事業環境の激変に対し、どういう風に対応するのかということは、本当に難しいことです。
特に、人の問題が重大です。現在、行政からは「雇用調整助成金なども活用し、雇用の維持に努めてください」などと大きく広報されています。
しかし、こうした助成金は従業員の方を休ませて、休業中に手当を支払うことで初めて受給できるものですので、要は働かない、利益を生み出さない状態で賃金を支払うという、経営的には異常な状態に対する緊急の補填だということです。
言うまでもありませんが、事業を維持成長し続けてこそ雇用の確保ができるのであって、そのためにどうしていくか、ということを緊急対応の次には必ず考えなくてはなりません。
根本的には、中長期的に最も重要なのは、こうした変化する時代において「人」をどう捉えるか、ということだと思います。
そして、現在の感染症の流行は、人に対して捉えなおす機会になり得るのではないでしょうか。
激変の時期は終わらない

コロナウィルス感染症の終わりの時期がいつになるのかは非常に見通しにくいことだと思います。専門家や行政サイドの意見にも通説といったものがありません。
この先2年は変わらず続くであろうという慎重な意見から、夏になるにしたがって早めに収束するという楽観論までさまざまなものがあります。まさに見通しにくい状況です。
しかし、経営や人事に携わる方が決して忘れてはいけないことは、こうした「経営環境が激変する時代になる」ということは近年ずっと言われて続けてきたことだということです。
気候変動や災害の発生や感染症の流行などの頻度が上がってきている、広まりやすい状況になってきている環境変化についてはよく言われてきました。
他にも、AIの進展や消費行動の変化、BtoB取引のマイクロマーケットが成立することによる取引相手の変動など、今までの企業戦略のあり方が根本的に変わり、変化のスピードが速まっているということは、今までもあらゆるところで言われてきたことではないでしょうか。
そして、これらは企業の規模や、業種業態を問わずに言えることです。
たとえば、飲食店がデリバリー事業を始めることが推奨されていますが、これは決して、感染症対応として一時的に行うような話でありません。
事業上の必要性があれば、今までも、いつでも行うべき事だったのではないでしょうか。
変化の時代なのだということは、変化に対応できない企業はとても弱い企業になってしまうということだと思います。
コロナウィルスの感染症による事業環境の悪化は、もしかしたらそこまで長く続かないかもしれませんし、とても長くなるかもしれません。
ただはっきりと言えることは、今回のような事業環境の激変が、いつ起きてもおかしくない時代に我々は既にいるということです。
そして、そういう変化の時にどういう風にするのか、また変化に対応していくためにどうするのかということまで考えておくことが、必要な時代になっているのだということです。
そして、こういう時に最も大事なことの1つが「人」をどういう風に変化に対応するものとして捉えるかということだと思います。
激変の時代に対応するための事業変革のための人事制度
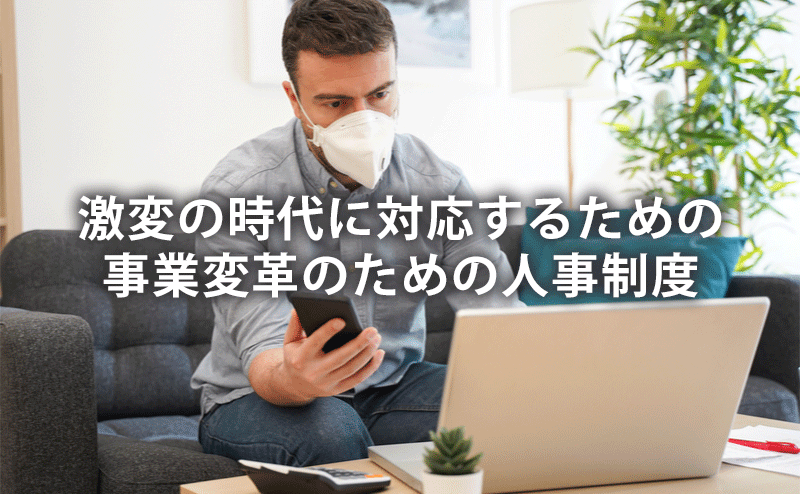
こうした時代において、どういう人事制度が必要なのか。この問いは難しいようで、根本的な答えは明らかだと思います。それは3点であり、
- 人事制度を変化に対応できるものにする
- 企業にいる内部と外部の人を分断せず、柔軟に用いられるようにする
- テレワークをはじめとする効率化・多様化に対応する仕組みの活用の最大化
です。
全て、今後の社会に対応できるようにするための必須の施策であると考えています。
そして何よりも、こうした施策を現時点でも徹底できている企業は、今回の感染症の流行での激変に対しても、対応力が極めて高いはずです。
今後の持続的な利益創出のための人材の活用方法であると考えます。
人事制度を変化に対応できるものにする
コロナウィルス感染症の流行の前から、全ての政策や社会的な人事のトレンドは、「個人の役割を変化させることができ、多様な働き方を成り立たせる」という方向に進んできています。
まず、「働き方改革」が行われてきましたが、これ自体が多様な働き方を促進するものであり、それぞれの働き方に応じた企業の施策が必要であるとされてきました。
また、人事制度においても、従業員の成長や技能、環境変化に応じた柔軟な配置転換や待遇変更を可能にするものであることが求められてきました。
一例として、企業規模を問わず活用できる「キャリアアップ助成金」の制度がもう8年以上続けられています。
この助成金は、一定以上の期間の勤務歴がある有期雇用の契約社員やアルバイト・パートの方を無期契約の正社員などに転換した時に報奨金が支給されるというものです。
こうした後押しもあり、アルバイトや契約社員から無期雇用の正社員に昇格する制度を持つ会社は一般的になってきました。
しかし、社員を評価する機能がうまく働いていなかったり、形骸化してしまったりしている企業も散見されます。
感染症対応のみに留まらず、今後も業態の転換・人員配置の柔軟な変更などを必要とする変化の機会は多いと思われます。
現在の緊急の状態でも、従業員の方に担当業務以外にも視野を広げていってもらうことで、チャンスに変えていくことはできるのではないでしょうか。
人材への見方を変えること、そのための手段としての人事制度への変更がいっそう望まれると思います。
企業にいる内部と外部の人を分断せず、柔軟に用いられるようにする
今回の感染症対応のように、急な業態変化を必要とする状態になったり、既存の社員の方も柔軟性を持って働くことが求められたりするような機会は今後も何度も出てくると考えられます。
そういう時に、下記のような形で人材が活用できたらどうでしょうか。
- 働く方が、事業環境の変化に主体的に対応できる
- 労働量の変化にも対応できる(具体的に言えば、自社での仕事量が減ったら外部で別業務を行うことができる)
- 業態の転換や事業の進展に応じて必要になった方を必要なだけ確保できる
こうしたことができたら、人事戦略としては夢のような話だと思います。
端的に言えば、既存社員の方への副業・複業制度と、外部の方を活用するための副業・複業制度を確立することができれば、こうしたことが可能になるのです。
ただし、単に作るだけではだめで、平時から主体的に副業が行われ、社員の方が成長しイノベーションをもたらすような、機能している制度でなくては、効果はありません。
既存社員の方に対する副業制度によって、事業の変化への対応力を上げることができます。
よく話し合いが必要ではありますが、副業の選択肢が増えた上で自社でも働いている社員の方と、非常のときには外部の業務の割合を上げ調整することもできるはずです。
また、外部の人材の活用はまさに非常時や業態転換時にとても重要で役に立つことでしょう。
こうした副業制度は、現在の緊急の状態においても役に立つものとも言えます。新しい見方で発想していくことが有効だと言えます。
テレワークはじめとする効率化・多様化に対応する仕組みの活用の最大化
感染症対応で、テレワークが一般的になりました。メリットも非常に多く、従業員の方からは、今後もある程度のテレワークは継続してほしい、という意見もよく耳にします。
しかし、特に管理者の方から「やっぱりリアルに出社した方がいい」という意見も耳にします。これはとても重要な現場実感ですが、大きな罠があります。何がそう思わせるのかを、絶対に一歩突っ込んで考えるべきところです。
ほとんどの場合、テレワークよりリアルの勤務の方が良いと思う欠陥は以下の3点のどれかであり、単なるテレワークの環境整備の不足であることが多いです。
-
在宅勤務のルール作りがはっきりしていない
-
ICT環境の整備が不足している
-
コミュニケーション手段の確保が十分でないこと
そして、メリットが非常に大きい事もしっかりと見据えることが必要です。
テレワークをやる・やめるの二軸で考えるのではなく、メリットとデメリットを整理し、課題を解決できる方法を考え、事業戦略・人事戦略として正当に位置付けていくことが必要だと思います。
コロナ感染症への対応に求められる起業家精神とチャンス
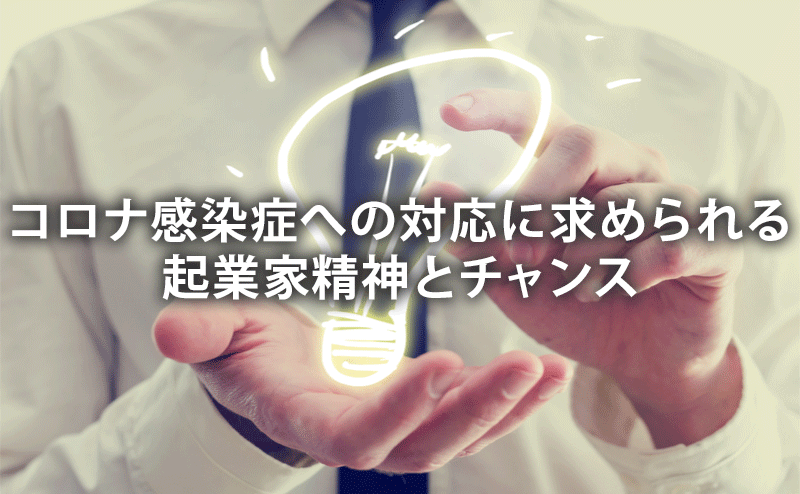
経営学者のドラッカーの晩年の名著「イノベーションと起業家精神」には、
-
社会が変動する時に最も強い組織は、変化できる組織である
-
イノベーションの原理は変化を当然のこととする行動であり姿勢である
というような言葉があります。イノベーションとは変化を大切にすることであり、変化自体が重要なのだ、という意味合いだと思います。
今こそ、感染症の流行に十分に対応しつつ、人事制度・副業制度・新しい働き方のあり方を整え、大きく飛躍していける機会にもなり得る、変化の時ではないかと思います。
次回から、今回の内容のさらに各論について掲載いたします。
関連記事
テレワークとは?コロナウイルス対策をきっかけに本格化する働き方改革プロジェクト 副業制度を創り活用するために④副業制度における社員の支援制度1
<こんな方におすすめです>
- 経営課題にマッチしたプロ人材が見つからず、課題が前に進まない
- ようやく見つけても、高額な年収がネックとなってしまう
- いざ採用して、もしも期待値以下だったらどうしよう、と不安になる
- ピンポイントな専門家を常時活用できるポジションの用意は難しい
- そもそもどんな人材が必要なのかわからない
ハイスキルシェアリング「プロの助っ人」では、年収800万円を超える通常は雇用が難しいハイクラス人材を、必要な時、必要な分だけ20万円~業務委託で活用できる新しい人材活用の形をご提案しています。
人件費はできるだけコストカットしたい。
しかし現状の社内の戦力だけでは経営課題の解決は難しい。
そんなときに「ピンポイントで助っ人に力を借りる」活用が、成長企業を中心に始まっています。
このような経営課題でお悩みの企業様は、是非ハイスキルシェアリング「プロの助っ人」にご相談ください。
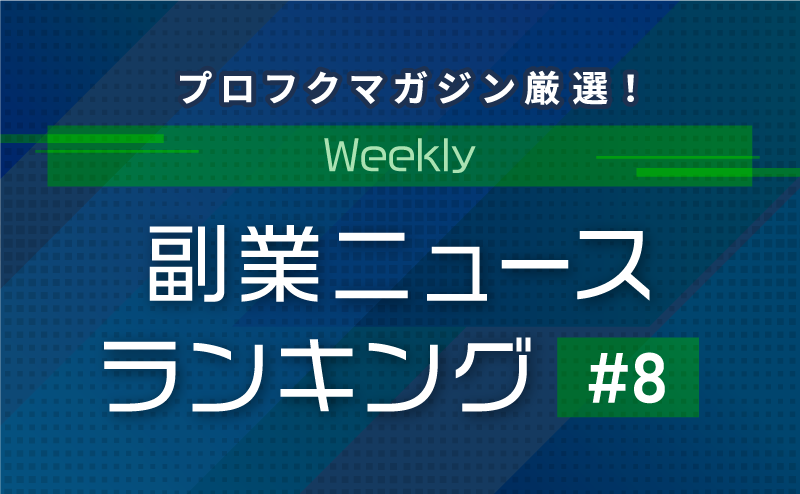 プロフクマガジン厳選!Weekly副業ニュースランキング 2020年5月2日~5月8日
NEXT POST
プロフクマガジン厳選!Weekly副業ニュースランキング 2020年5月2日~5月8日
NEXT POST
 【副業女子インタビュー】パラレルワーカーちゃきさん「子育てと仕事の両立は複業で叶う!」
【副業女子インタビュー】パラレルワーカーちゃきさん「子育てと仕事の両立は複業で叶う!」
関連記事 RELATED POSTS
-
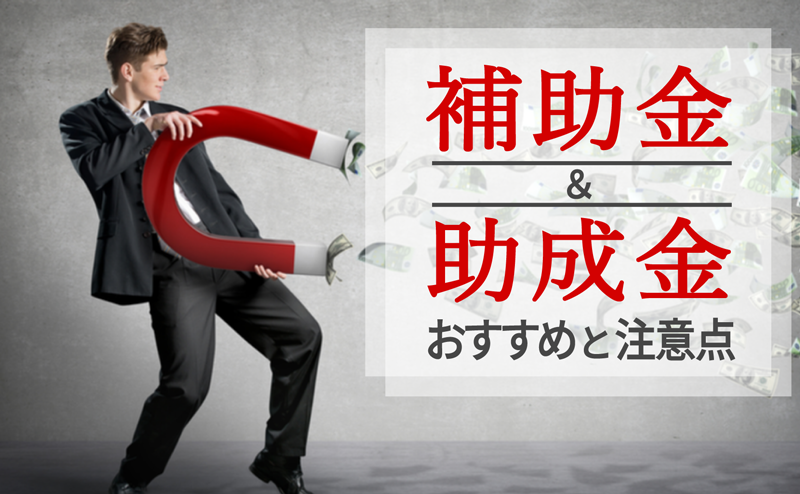
-

-
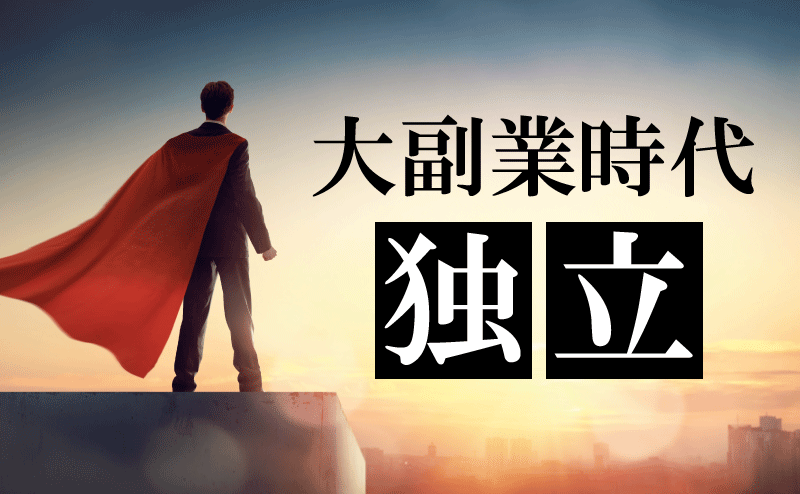
-

-
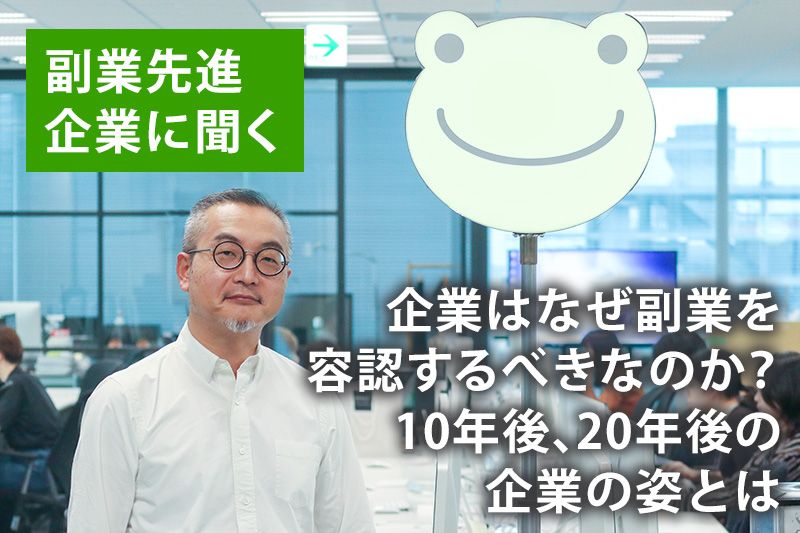
-



